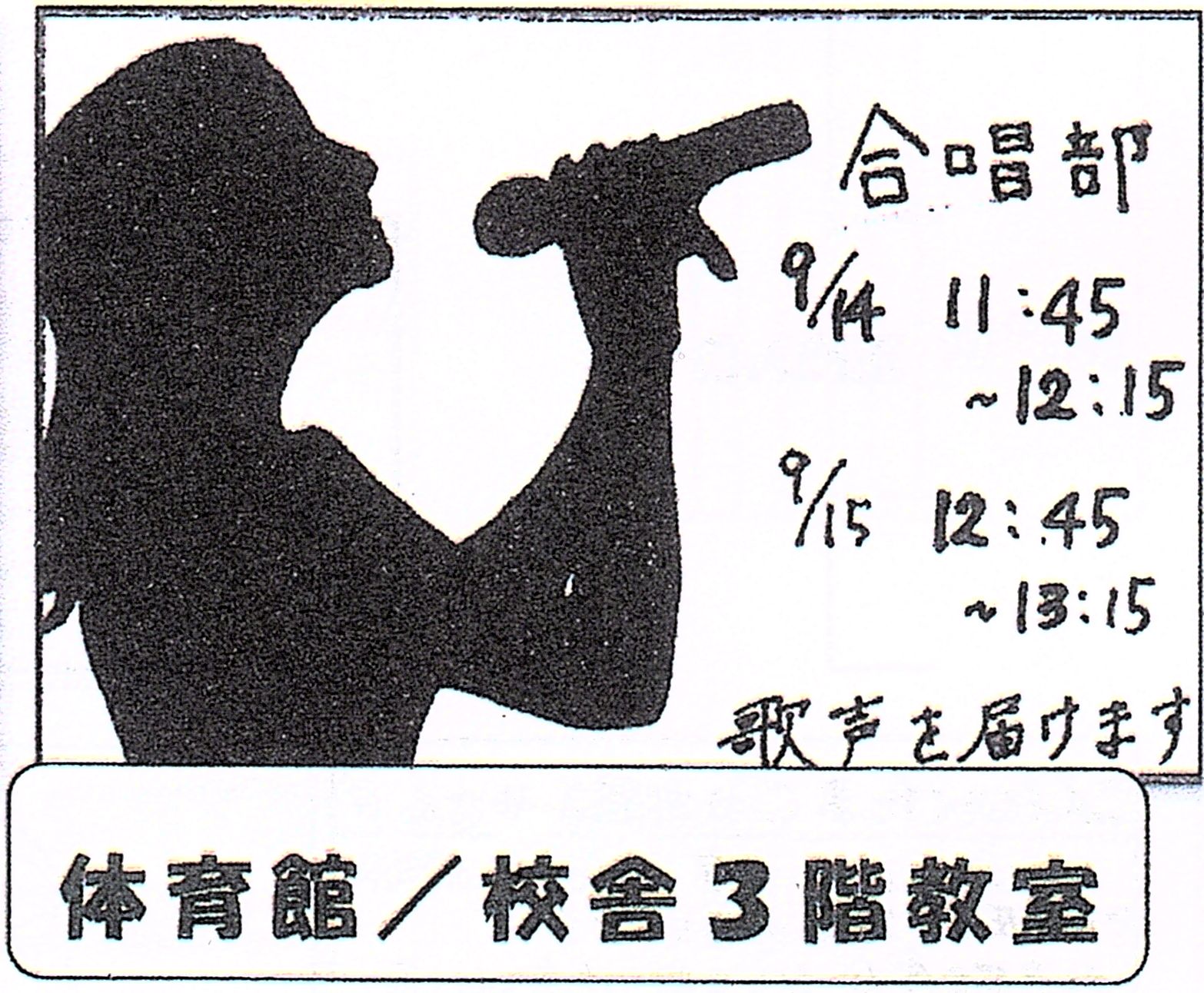本日、朝から雨模様。沢歩きや藪漕ぎの可能性が低い神社巡りにすることにして、三浦に向いました。
【主な経路】
(三崎口駅)-引橋-白髭神社-稲荷社(諸磯1785)-諸磯神明社-諸磯遺跡碑-稲荷社(諸磯1245)-(海外町)龍神社-竜王祠-(白石町)龍神社-(ニ町谷)神明社-あきや様-三崎住吉神社-元宮神社-(三崎)龍神社-(三崎)稲荷神社-秋葉神社-不明の社-紀代-城ヶ島入口-(三崎口駅)
【白髭神社】三崎町小網代1793
長安寿老人(白髭神社)
この白髭神社は、小網代湾が昔から廻船寄港地、また三崎の避難港として全国的に知られていた関係上、航海安全大漁満足の神としても古くから崇拝されてきました。
天文年間(1532~55)、当時の漁夫の夜網のかかった霊光まぶしく光る束帯姿の御神体をお祀りしたと伝えられますが、祭神は海上安全の神
寿老人は長寿を授けるというので、信仰する人が昔からまことに多かったといわれています。
社殿の前にある石は磐石といい、打てばかんかんと金属性の音がするので一名「カンカン石」とも呼ばれていますが、これは「きごいかり」という錨のおもりで、海上安全のために昔摂津の船頭が明神様がその石ほしいというので社に奉納したものと伝えられています。
三浦市
The God of Longevity Shirahige Shinto Shrine
This Shirahige Shinto Shrine form a long time ago has been a port of call at Koajiro bay, and it has also been known nationally as a harbour of a refuge for Misaki. For a long time this shrine has been worshipped as a place of goods for safe voyage and a large catch for the fisherman of Misaki.
During the Tenmon Period (1532-1555), the story is told that while night fishing with nets the fisherman of this village saw a holy light shining in the water in which a figure dressed in traditional, ceremonial court clothing and was beleived to be a shintai, or an object of worship beleived to contain the sprit of a deity, appeared. the enshrined deity was for marine safety by the god Nakatsutsuo no mikoto, also known as the miracle-working, gray-mustached god.
Because the God of longevity is said to grant long life, from a long time ago it is siad that many people truly had great faith.
The rocks in front of the main shrine are called keiseki. If you tap on them, they will make a clanking, metallic sound that like “Kankan.” Brcause of this, they are also called “kankan rocks.” The rock were found to be from anchors for marine safety for boatman desired by the miracle-working god who needed the rock, thus the rocks are kept as a dedication at the shrine.
Miura City
【稲荷社】三崎町諸磯1785
【諸磯神明社】三崎町諸磯1872
諸磯神明社由緒
御祭神 主祭神 天照皇大神
合祀神 日本武尊 大山咋命
御神徳 家内安全 五穀豊穣 海上安全 大漁満足
境内社 八幡神社 誉他別尊
浅間神社 木花咲耶姫命
猿田彦神社 猿田彦尊
稲荷神社 宇迦之御魂尊
御由緒 当社は建久・正治年間(一一九〇~一二〇〇)に伊勢地方から移住した人々が伊勢神宮を勧請したのが始まりとされている。明治の終わりから大正の始めにかけて白鳥神社、日枝神社を合祀した。明治六年、諸磯の鎮守として「村社」に列格され、大正二年に神饌幣帛料供進神社に指定された。
年中祭事 祈年祭 四月四日
例大祭 九月四日(四年に一度、神輿渡御)
新嘗祭 十一月二十五日
【稲荷社】三崎町諸磯1245
【龍神社】海外町10
【竜王祠】白石町22
【龍神社】白石町22
【あきや様】三崎5丁目16-3
【二町谷神明社】(山中大六天神社、稲荷社):白石町15-1
山中大六天神社
三浦郷土誌に依る由来-
明治初期半次郎九六代目石渡庄次郎が大六天の霊験あらたかを知らされ三崎町諸磯村白州のがんだ山の大松の根元に祠を祀り其の後、孫の半蔵氏が詞と石段を寄進した。
平成元年末より同地域の造成計画によりニ町谷神明社役員一同様の御理解と御厚意なて此の地に鎮座復元する。
平成元年十二月十七日
三浦市白石町半次郎九十九代
石渡喜太郎健之 六十七才
弟妹子供一同
【稲荷社】(庚申塔):三崎5丁目8
【三崎住吉神社】三崎5丁目8
【花暮竜宮社】三崎3丁目12
【元宮神社】三崎3丁目9
元宮神社
御祭神藤原資盈公は藤原鎌足の後裔で、五十六代清和天皇の皇位継承の争いに関係した伴大納言善男の謀挙に加担しなかったため、善男と不和になり、故あって九州博多を出港し、貞観六年(九六四年)十一月一日当地に着岸されました。その後、付近の海賊を平定したり。里人を教化し文化の礎を築きました。よって里人の尊崇の念篤く、公の没するやそのなきがらを海に沈め祠を建立し祀ったのがこの神社です。毎年正月十五日に奉納される歌舞「ちゃっきらこ」は資盈公の妃盈渡姫が土地の娘達に教えたとの口碑があり、昭和四十五年五月、県の無形文化財、同五十一年五月、国の重要無形民俗文化財に指定されました。
三崎まちなみ事業協議会
【仲崎龍神社】三崎2丁目1南側(2016.2.13撮影)
【龍神社(推定)】三崎2丁目1北側
【子育稲荷大明神】三崎4丁目18
【秋葉山神社】本瑞寺境内社:三崎1丁目19-1
【由緒不明の社】
以下、本日撮影の写真です。
カラスザンショウ Fagara ailanthoides
マテバシイ Lithocarpus edulis
キダチチョウセンアサガオ Brugmansia suaveolens
イチジク Ficus carica
小網代配水塔:小網代2192-3
ノカンゾウ Hemerocallis longituba
石塔群:三崎町小網代158-3
Narrow-leaved Ragwort(?) Senecio inaequidens
小網代湾
タイワンリス Callosciurus erythraeus thaiwanensis
ヤブミョウガ Pollia japonica
イチイ Taxus cuspidata
油壷湾
六地蔵:三崎町諸磯1744(浜の原バス停前)
庚申塔:三崎町諸磯1797
道路改修記念碑
庚申塔群:三崎町諸磯1241
諸磯遺跡碑
石塔群(地蔵、観音、西国巡り記念):三崎町諸磯1058
石塔群(庚申塔3基、馬頭観音2基)
海外町のスランプ構造
白石地蔵尊:白石町17
うらりマルシェ
三崎館本店
にじいろさかな号
石塔群:三崎4丁目18
紀の代
雨の城ヶ島入口
島の娘:小川清彦作
シラハギ Lespedeza thunbergii subs. thunbergii f. alba
諸磯遺跡
ここ新堀 白須 屋志倉にまたがる台地一帯をいう縄文前期の諸磯式土器の標準遺跡として有名である。また西南隅からは竪穴住居も発見された。
昭和五十二年三月吉日 三浦市教育委員会