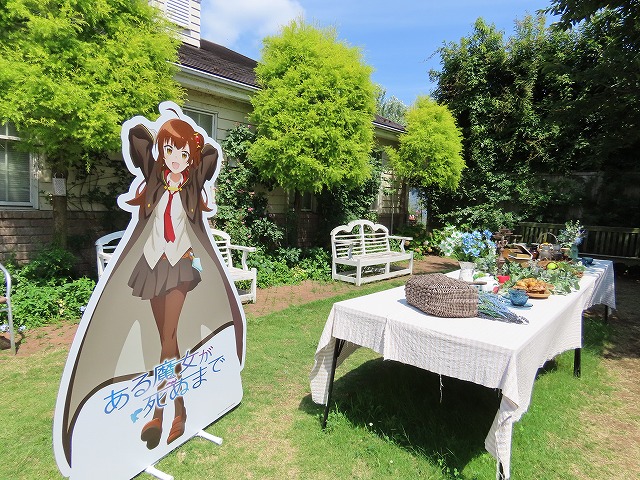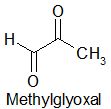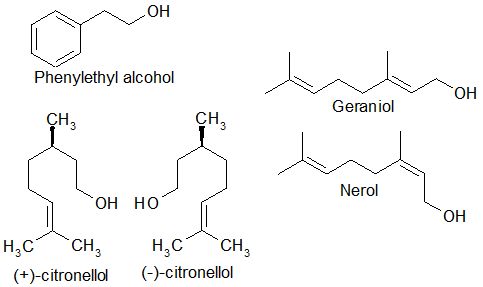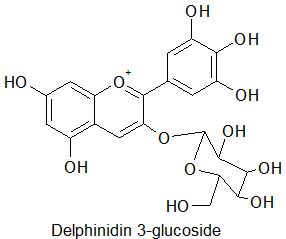ハスの花の季節には早朝開園しているとのウェブ情報を見かけたので、朝一で大船フラワーセンターを尋ねました。園内ではニイニイゼミが鳴きだしています。
ハス科 2023-06-18 現生植物 現生生物 後世動物
【本日更新のページ】バラ科 キジカクシ科 トケイソウ科 ヤマモガシ科 膜翅目 鞘翅目
【蓮】
ウォレマイ・パイン Wollemia nobilis Wollemi Pine
ハス Nelumbo spp.

ウォレマイ・パイン Wollemia nobilis Wollemi Pine

紅蜀紅蓮

玉鶯

朱雀の舞姫

玉繍ぎょくしゅう

玉繍蓮

喜上眉梢

絢爛華

西村白

巨椋大島

巨椋の曙

巨椋の香

巨椋瑞光

巨椋の彩雨

常楽

春不老

多彩

輪王蓮

美中心

不忍池斑蓮

瑞姫

花火

黄陽

アルバ・グランディフローラ ‘AlbaGrandiflora’ (?)

乗県碧蓮

天竺斑蓮

紅がに

白白蓮

悄英

舞妃蓮

飛舞蓮

ローズプレナ ‘Rose Plena’

丈炎の舞

常陸の曙

大灑錦

暁風涼月

西円寺青蓮

カロライナ・クイーン ‘Carolina Queen’

ミセス・スローカム ‘Mrs. Slocum’

玉葉黄

花雲淡紅

アメリカ黄蓮

雲之霞

オハイオ蓮

漁山紅蓮

古楚女

大空蓮

大内池

インド白蓮

仏足蓮

明妃

宮西

友誼牡丹

大賀蓮(種子系)

重水華

黄玉杯

白万葉

唐招提寺蓮

玉泉寺妙蓮

奈良蓮

白君子小蓮 (?)

ペリーズ・ジャイアント・サンバースト “Perry’s Giant Sunburst”

斑桃 (?)

寿星桃

詩仙堂西湖蓮

剣舞蓮

毎葉蓮

御所車

金輪蓮

西福寺観世

即非蓮

植松10

粉松球

(突然変異)

紫玉蓮

赤大君子

天照爪紅

天嬌

廬山白蓮

植松球

神采

碧翠蓮

小舞妃

小金鳳

揚州碗蓮

祥隆紅蓮
大船フラワーセンターにハスが来た経緯
大船フラワーセンターは2020年1月静岡県沼津市の本廣寺の関戸慈誠住職から約190品種のハスを譲り受けました。関戸住職は前任の蓮興寺(静岡県沼津市)で約30年間ハスを育ててきましたが、栽培の継続が困難になり、新しい担い手を探していらっしゃいました。2019年、当園の園長である榎本浩が栽培の引継ぎを申し出たところ、譲渡を快諾していただきました。
2024年には大阪市のこの花咲くや館、及び蓮文化研究会から合計20品種のハスを譲り受けるなど、当園にて管理を行っていたハスと併せて、現在261品種のハスを園内に転じ字ています。
大賀ハス
日本では非常に有名はハスで、1951年千葉の検見川の東京大学厚生農場の敷地内から縄文時代(約2000年前の地層)の丸木舟が発見され、大賀博士は多くの協力者を得て、その地下から3個のハスの実を発掘しました。そのうちの1個が発芽・開花しました。大賀博士にちなんで命名され平和のシンボルとして世界各国に株分けされています。花はピンク色で条線がぼやけており、葉の表面が触ると他の品種に比べてすべすべとした感触があります。別名「二千年蓮」。
大賀ハスは、実生、即ち発芽種子から育成すると、外観上の形質が大きく変化することが知られています。ここで展示されているのは種子系だけの様でした。
大賀ハス(こども植物園)
珍しいハス
○植松家系
沼津の植松家の代々受け継がれてきたコレクション。一般には出回っていないので名前が付いていません。植松家の祖先は武田氏の宿將須田朝重で、武田が敗れたあと、朝重の嫡男李重が天正十二年(1584)年に居を決め、沼津で開墾や植林にいそしみ花卉類の収集もしました。花長者として有名になり、庭も帯笑園と名付けられ江戸に下る公家や大名、または明治政府の官僚、皇后、皇太子などが立ち寄り花卉類と京文化の交換の場となりました。
○大石寺系
日蓮宗総本山の大石寺で昔から受け継がれてきたハス。一般に出回っていません。「大石NO. 」というのがそのまま正式名称になっています。
○巨椋池系
巨椋池とは戦前まではハスの名所として世に知られた池です。現在の京都市、宇治市、久世郡
久御山町にまたがり、面積約800ヘクタールにも及んだところでしたが、
農地・水田として埋め立てられ、今はありません。現在交通の要衝ともなっています。
池であった当時、面積100ヘクタールほどのハスの群生地が広がっていました。この広さは
中国の著名な蓮池にも匹敵します。池跡地の田んぼを巡り採取した幼芽を育成した蓮が巨椋池系と呼ばれています。巨椋池系の品種は約90種類ほどあります。
ハス
Nelumbo nucifera、キバナハス
Nelumbo lutea
紅蜀紅蓮
玉鶯
朱雀の舞姫
玉繍
玉繍蓮
喜上眉梢
絢爛華
西村白
巨椋大島
巨椋の曙
巨椋の香
巨椋瑞光
巨椋の彩雨
常楽
春不老
多彩
輪王蓮
美中心
不忍池斑蓮 瑞姫
花火
黄陽
アルバ・グランディフローラ ‘AlbaGrandiflora’ (?)
乗県碧蓮
天竺斑蓮
紅がに
内側の縮れた花弁の形がカニの手のように見えることから「紅がに」と名付けられた。内田又男氏が育成したもの。中盤(荷鼻)の形は下の点々が大きく流れる模様となり、荷鼻から判断できるハスでもある。
素白蓮
悄英
舞妃蓮
大賀蓮と王子蓮の交配種、優雅な舞姿を連想させることから妃殿下にイメージを重ねて、「舞妃蓮」と名付けられる。昭和43年に東宮御所に献上された。
飛舞蓮
ローズプレナ ‘Rose Plena’
丈炎の舞
常陸の曙
大灑錦
暁風涼月
西円寺青蓮
カロライナ・クイーン ‘Carolina Queen’
ミセス・スローカム ‘Mrs. Slocum’
玉葉黄
花雲淡紅
アメリカ黄蓮
雲之霞くものかすみ
オハイオ蓮おはいおばす
漁山紅蓮
花色は桃色で条線は鮮明。漁山は声明(僧が仏の徳をたたえて節をつけて唱える)の起源地として伝説に残る中国の地。DNA分析では、現在伝わる藤壺蓮、浄台蓮、漁山紅蓮、桜蓮は、同一と判定された。これらは、形質的にも極似している。
古楚女
大空蓮
大内池
インド白蓮
仏足蓮
明妃
宮西
友誼牡丹
大賀蓮(種子系)
重水華
黄玉杯
白万葉
唐招提寺蓮
玉泉寺妙蓮
奈良蓮
白君子小蓮 (?) ペリーズ・ジャイアント・サンバースト “Perry’s Giant Sunburst”
斑桃 (?)
寿星桃
詩仙堂西湖蓮
剣舞蓮
毎葉蓮
花上りが非常に良いのが特徴。ハスは節から一対の葉と花を上げてくるが、実際には花の方はすべてが上がってくるわけではない。しかし、本品種はそのすべての葉ごとに花が上がるほど花付がいいという意味で毎葉蓮の名が付いた。
御所車
金輪蓮
西福寺観世
即非蓮
植松10
大石寺23
植松03
植松02
大石寺08
植松19
大石寺21
粉松球
(突然変異)
紫玉蓮
赤大君子
天照爪紅
天嬌
廬山白蓮
植松球
神采
碧翠蓮
小舞妃
小金鳳
揚州碗蓮
祥隆紅蓮

デンティ・ベス ‘Dainty Bess’

ピース ‘Peace’

ゴールデン・チャッピー ‘Golden Chappy’

ピンク・サクリーナ ‘Pink Sakurina’

カウンティ・フェア ‘County Fair’

マチルダ ‘Matilda’

シークレットロパフューム ‘Secret Perfume’

ミセス・オークリィ・フィッシャー ‘Mrs. Oakley Fisher’

フラウ・ホレ ‘Frau Holle’

金蓮歩 ‘Kinrenpo’

ティファニー ‘Tiffany’

オリンピック・ファイヤー ‘Olympic Fire’

桜貝 ‘Sakuragai’

ロサ・ギガンテア Rosa giganrea Manipur Wild-Tea Rose

ロサ・キネンシス・ミニマ Rosa chinensis var. minima

イザヨイバラ Rosa roxburghii

ノイバラ Rosa multiflora
バラ
Rosa
デンティ・ベス ‘Dainty Bess’
ピース ‘Peace’
ゴールデン・チャッピー ‘Golden Chappy’
ピンク・サクリーナ ‘Pink Sakurina’
カウンティ・フェア ‘County Fair’
マチルダ ‘Matilda’
シークレットロパフューム ‘Secret Perfume’
ミセス・オークリィ・フィッシャー ‘Mrs. Oakley Fisher’
フラウ・ホレ ‘Frau Holle’
金蓮歩 ‘Kinrenpo’
ティファニー ‘Tiffany’
オリンピック・ファイヤー ‘Olympic Fire’
桜貝 ‘Sakuragai’
○ロサ・ギガンテア
Rosa giganrea Manipur Wild-Tea Rose
ロサ・キネンシス・ミニマ
Rosa chinensis var.
minima
イザヨイバラ
Rosa roxburghii
ノイバラ
Rosa multiflora
【擬宝珠】

レンゲギボウシ(黄覆輪) Hosta X fortunei

コバギボウシ Hosta sieboldii syn. Hosta albo-marginata

ギボウシ属の一種 Hosta sp.

ホスタ・ウィリーニリィ Hosta cv. ‘Willy Nilly’

マルバノタマカンザシ Hosta plantagina

ホスタ・ハルシオン Hosta cv. ‘Halcyon’

ホスタ・シャンデー Hosta cv. ‘Shandy’

オハツキキボウシ(白覆輪) Hosta undulata var. Erromena

ホスタ・シェードファンファーレ Hosta cv. ‘Sade Fanfare’

タチギボウシ(黄中斑) Hosta sieboldii var. rectifolia Erect Hosta

トクダマギボウシ(斑入り) Hosta sieboldiana var. condensata

黄金姫トクダマ Hosta sieboldiana ‘Tokudama Aureonebulosa’

スジボウシギ Hosta undulata Wavy Plantain Lily

黄金コバギボウシ Hosta sieboldii ‘Ougon’

オオバギボウシ Hosta sieboldiana

ギボウシ属の一種 Hosta sp.

ホスタ ‘武州錦’ Hosta ‘BushuNishiki’
レンゲギボウシ(黄覆輪)
Hosta X
fortunei
コバギボウシ
Hosta sieboldii syn.
Hosta albo-marginata
ギボウシ属の一種
Hosta sp.
ホスタ・ウィリーニリィ
Hosta cv. ‘Willy Nilly’
マルバノタマカンザシ
Hosta plantagina
ホスタ・ハルシオン
Hosta cv. ‘Halcyon’
ホスタ・シャンデー
Hosta cv. ‘Shandy’
オハツキキボウシ(白覆輪)
Hosta undulata var.
Erromena
ホスタ・シェードファンファーレ
Hosta cv. ‘Sade Fanfare’
タチギボウシ(黄中斑)
Hosta sieboldii var.
rectifolia Erect Hosta
トクダマギボウシ(斑入り)
Hosta sieboldiana var.
condensata
黄金姫トクダマ
Hosta sieboldiana ‘Tokudama Aureonebulosa’
○スジボウシギ
Hosta undulata Wavy Plantain Lily
黄金コバギボウシ
Hosta sieboldii ‘Ougon’
オオバギボウシ
Hosta sieboldiana
ギボウシ属の一種
Hosta sp.
ホスタ ‘武州錦’
Hosta ‘BushuNishiki’

ヤマグルマ Trochodendron aralioides

プラタナス Platanus sp.

アエスクルス・パルウィフロラ Aesculus parviflora

ニホンミツバチ Apis cerana japonica

マメコガネ Popillia japonica

シロタエギク Jacobaea maritima

イヌタヌキモ Utricularia tenuicaulis

ギャラックス・ウルセオラタ Galax urceolata

ウォーターバコパ Bacopa caroliniana

マルバデイゴ Erythrina crista-galli ‘Maruba-Deigo’

ムサシアブミ Arisaema ringens

ウラハグサ Hakonechloa macra

ハアザミ Acanthus mollis

ネムノキ Albizia julibrissin

チョウセンアザミ(カルドン) Cynara cardunculus

セイヨウニンジンボク Vitex agnus-castus

ヒマワリ Helianthus annuus

カンレンボク Camptotheca acuminata

テイキンザクラ ‘ホコバヤトロファ’ Jatropha integerrima

キバナキョウチクトウ Thevetia peruviana

ペトレア・ウォルビリス Petrea volubilis

シクシン Combretum indicum

キフゲットウ Alpinia zerumbet ‘Variegata’

パイナップル Ananas comosus

パッシフローラ・サンギノレンタ Passiflora sanguineolenta Blood Red Passion Flower

ステノカルプス・サリグヌス Stenocarpus salignus Scrub Beefwood

ケヤキ Zelkova serrata
ヤマグルマ
Trochodendron aralioides
プラタナス
Platanus sp.
アエスクルス・パルウィフロラ
Aesculus parviflora
○ニホンミツバチ
Apis cerana japonica
○マメコガネ
Popillia japonica
シロタエギク
Jacobaea maritima
イヌタヌキモ
Utricularia tenuicaulis
ギャラックス・ウルセオラタ
Galax urceolata
ウォーターバコパ
Bacopa caroliniana
マルバデイゴ
Erythrina crista-galli ‘Maruba-Deigo’
ムサシアブミ
Arisaema ringens
ウラハグサ
Hakonechloa macra
ハアザミ
Acanthus mollis
ネムノキ
Albizia julibrissin
チョウセンアザミ(カルドン)
Cynara cardunculus
セイヨウニンジンボク
Vitex agnus-castus
ヒマワリ
Helianthus annuus
カンレンボク
Camptotheca acuminata
テイキンザクラ ‘ホコバヤトロファ’
Jatropha integerrima
キバナキョウチクトウ
Thevetia peruviana
ペトレア・ウォルビリス
Petrea volubilis
シクシン
Combretum indicum
キフゲットウ
Alpinia zerumbet ‘Variegata’
パイナップル
Ananas comosus
○パッシフローラ・サンギノレンタ
Passiflora sanguineolenta Blood Red Passion Flower
○ステノカルプス・サリグヌス
Stenocarpus salignus Scrub Beefwood
ケヤキ
Zelkova serrata
【文献】
日本花蓮協会 (2015) 日本で栽培されている品種, URL:
http://www.j-lotus.org/hanabunrui/7%20sirohitoe.htm, Accessed: 2025-06-30.
久保中央, 金子明雄, 山本和喜 (2015) SSRマーカーに基づく巨椋池系品種群を含む日本国内花蓮品種の分類, 育種学研究, 17, 45–54, DOI:
10.1270/jsbbr.17.45, Accessed:2025-06-30.